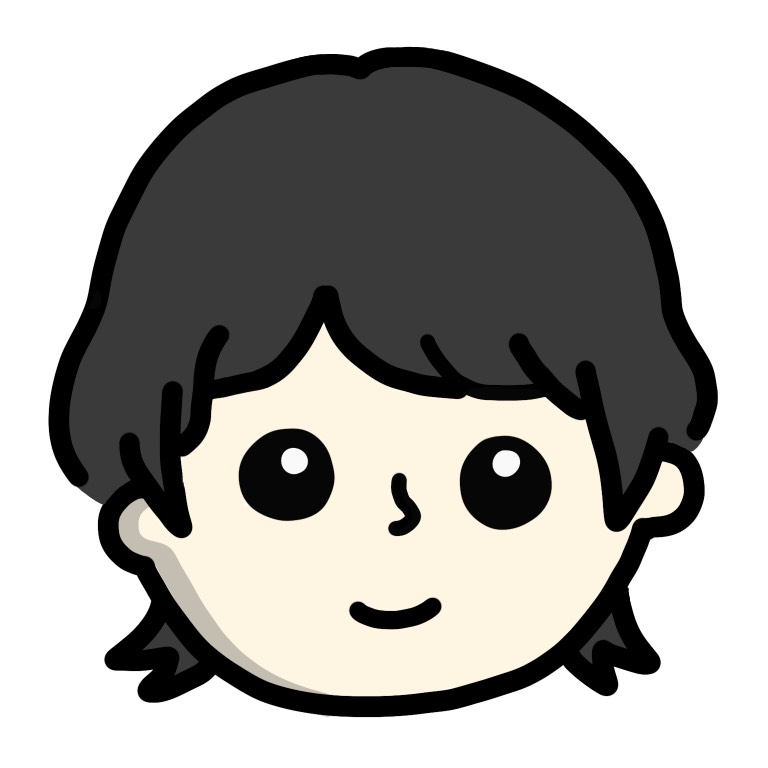投資をやる上で、損が出ることは誰しも経験することですが、損が続くと不安になってしまう人も多いと思います。
そこで今回は、損が出ても冷静に対処するための考え方や、そもそも損が続かないためにはどうすればいいのか、お話ししていきたいと思います。
目次
損をしないポートフォリオ作り

そもそも損をしないポートフォリオを組むということが大事です。
損が続くということは何かしら問題があるということです。
運用が上手いから損が続かないとか、下手だから損失ばかり出すという問題ではありません。
要するにヘッジができていないということです。
本来ヘッジができているポートフォリオであれば、一方が損失を出しても、どこかがそれを補ってくれるという形になるはずです。
もしヘッジという概念なく投資をやっていたら、そもそも丁半博打みたいなものです。
損失を出してくださいと言っているようなものです。
自分なりにヘッジを考えて組んでいるポートフォリオであれば、なぜヘッジが働かなかったのかをまず考えることです。
あとは損が続いても死なないようにするということです。
レバレッジをかけた投資をしないことです。
(レバレッジ投資については、下の記事でお話ししていますのでそちらも合わせてお読みください。)
いくら損が続いても退場しなければ、次またリベンジできるので、一発退場は一番避けなければいけません。
損する前から一発退場しないためのポートフォリオの組み方とは何か。
それは分散投資です。
一つのものに対して多くの資金を投入してしまうとしんどくなります。
有望な企業はいくらでもあるので、そういったものに対してきちんと分散投資をすることです。
損失の原因をきちんと解明する
損が続いたとしても、自分が本当に有望だと思っている会社に投資をしていたら、いつか上がるはずです。
損切りした途端に上がっていって、売らなければよかったということもよくあると思います。
損が続いた時にどうするかというより、損失が起きることに対してどれだけ準備ができているのか、まずはそこから考えていく必要があります。
もしその上で、損失が続いてしまった場合、相当何か今までにないことが起きているということです。
基本的に、私がやっている資本主義に対して投資をするやり方は、今まで長期に渡って損が続く出来事が起きたことがあまりないです。
(資本主義に対して投資をするやり方について、下の記事でお話ししています。)
続いたとしても、せいぜい数年です。
根本的に損失が続くサイクルに入ってしまうということは、そもそも前提が崩れてしまっている可能性があります。
前提が崩れてしまっているのであれば、問題は深いです。
そのためまず前提が崩れているのか確かめます。
崩れていないのであれば、どこかで戻ると自分のポートフォリオに自信を持つことです。
私も損失を出している銘柄はありますが、個人的に失敗しているなと思う銘柄は、世の中の流れを掴んでいない銘柄です。
例えば、今であれば米国の百貨店系の銘柄を持っていますが、厳しい状況です。
百貨店はコロナの影響を受けていて、それによってアマゾンなどのECにさらに拍車がかかった中で、もう立ち上がれないと見ています。
そういう理由がはっきりあれば損切りのタイミングを考えるべきです。
そうではなく、今後ここは伸びるはずだというのがあるのなら、ある程度含み損を抱えていても、確定するまでは損失ではないので保有する形でいいと思います。
損が出て不安にならないために準備しておくこと

そうは言っても、目の前に損失が拡大していく状況を目の当たりにして、不安になることもあると思います。
そんな時に支えになるのは、やはり自分の投資哲学を持って、それを信じ続けられるかどうかです。
(投資哲学については、下の記事をご参考にしてください。)
株式にしても不動産にしても勝ち続けることはできません。
どこかで負けるタイミングは来ます。
負けたときに自分の投資哲学を信じられるかどうかが大きな問題です。
信じられるかどうかはやはりそれまでの準備に起因します。
しっかりとした準備をしたからこそ、ポートフォリに自信が持てるのだと思います。
投資は信じられるか信じられないかの戦いだということです。
何%上がったら売って、何%下がったら損切りをしてというように、機械的にルールを決めているのならそのルールでやればいいと思います。
短期投資ではそういったルールでやっている人が多いかもしれません。
ただ自分には短期投資は向いていないので、あくまで長期投資において機械的にルールを決めるということはしません。
基本的に資本主義に対する投資というのは、何%上がったら売るというより、資本主義を信じるということです。
そもそも損切りや、利益確定という考え方があまりないです。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
損が続くといつも不安になるという方は、自分なりの投資哲学を持ってポートフォリオを組む準備ができているか、改めて考えていただくといいのではないかと思います。
少しでもご参考にしていただけますと幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。